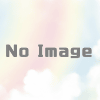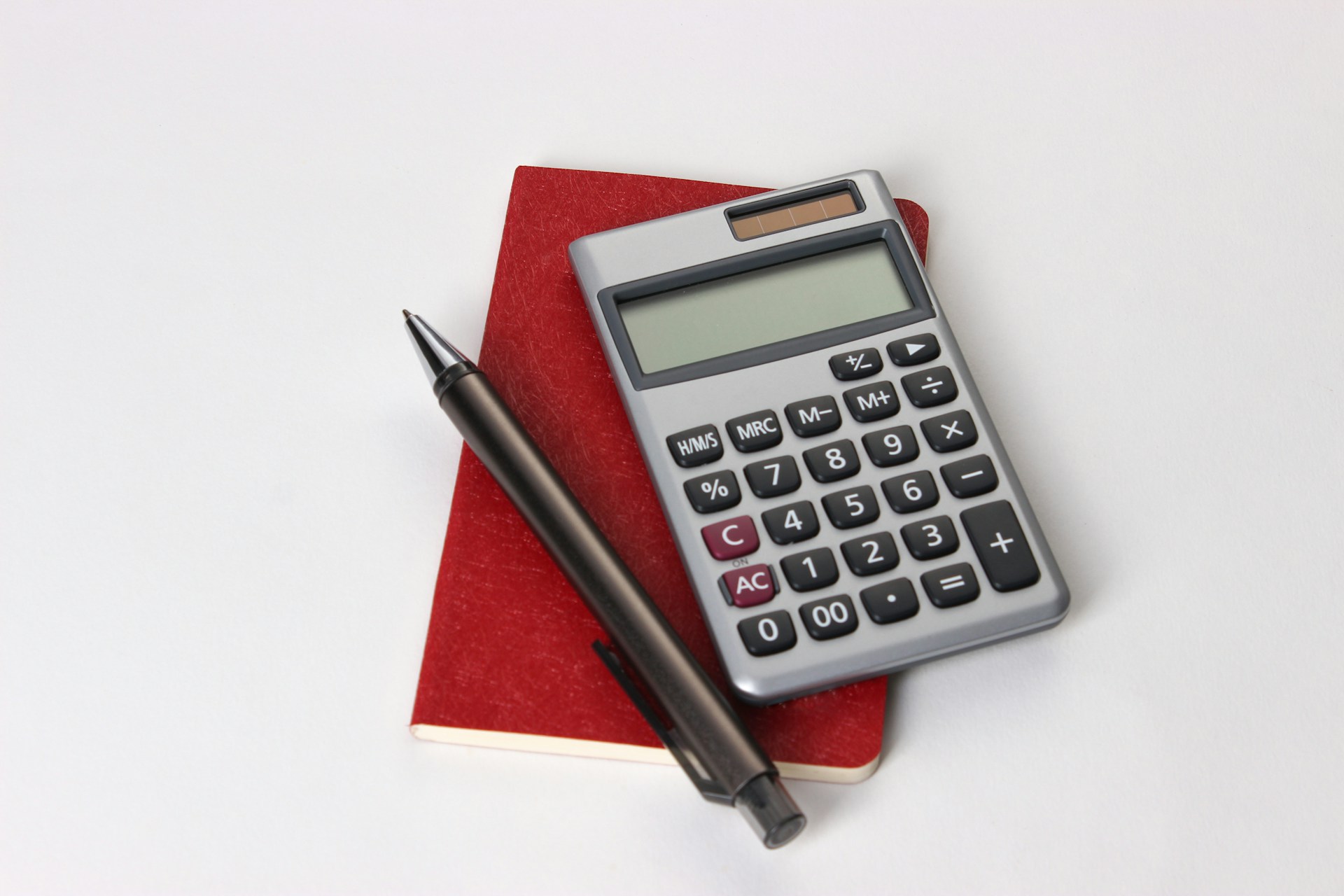
【独学でも合格可能】簿記の資格で転職を成功させよう
簿記の資格は、経理や会計の仕事に携わる際に役立つスキルです。
未経験者・経験者問わず、資格があれば転職時のアピール材料にもなります。
今回は、簿記の魅力や勉強方法、転職との関係性について解説する記事をお届けします。
簿記初学者の方も、すでに勉強中の方もぜひ参考にしてみてください。
簿記の資格があると何をアピールできる?
まずは、簿記の資格が実務で役に立つシーンをご紹介します。
もっとも一般的な活躍の場としては、経理の仕事が考えられるでしょう。
日常の仕訳入力から年次の決算業務まで、幅広く対応できます。
また、経理の人材はどの業界でも必要とされる点もポイントです。
仕訳入力、帳簿作成など経理事務に活用可能
簿記の試験範囲には日常の仕訳処理が網羅的に含まれており、経理処理への理解が深まります。つまり、簿記の資格を取得していれば、仕訳と経理の仕組みを一定のレベルで理解していることの証明になり、転職の際にアピール材料として活用できます。
さらに、出納や棚卸など、一般事務に役立つ知識も学習できるため、幅広い仕事に対応するスキルの習得が可能です。
日常事務だけでなく、決算にも対応可能
簿記の資格は、決算業務においても役立ちます。企業では年に一度、1年間の取引をまとめる決算を行いますが、在庫管理や未払金、前払費用の処理など、決算整理も簿記の試験範囲です。
決算業務は確定申告の期限を踏まえて取り組むため、ある程度の人手と作業時間が必要となります。決算に対応できる簿記資格者のスキルは特に需要が高いでしょう。
経理・会計のポジションは各業界に必須
経理業務はすべての会社に存在します。規模や取引によって求められるレベルの差はありますが、どの会社にも「経理担当者」は存在するといっても過言ではありません。つまり、簿記の資格を取得しておけば、幅広い業界での転職時に通用するスキルとして活用できます。
業界を問わず活躍の機会を模索できるため、キャリアの幅は大きく広がるでしょう。
独学で簿記の資格を取得するには?
ここからの話題は簿記の学習方法に移ります。
簿記には資格学校や通信講座なども存在しますが、個人的には独学がおすすめです。
テキストと問題集のみ購入して独学で進めると、最低限の出費に抑えられます。
ただし、学習の計画づくりは最低限必要でしょう。
学習スケジュールの策定と実践
独学で簿記の学習を進めるには、勉強時間やスケジュールの管理が重要です。月単位、週単位、1日単位と細かく分類して計画を立てると、勉強量をタスク的に捉えることができます。自分の生活リズムや着手時間を計算に入れると、無理のないペースで学習を積み上げられるでしょう。
立てた計画を実践したうえで、学習量やペースに適宜改善を加えると学習の効率化が図れます。
テキストや問題集、各コンテンツをフル活用
学習方法として、独学では直接講義を受けない代わりにテキストや問題集をフル活用することが重要です。テキストは1周目で流し読みし、全体の流れを把握したうえで、2回目以降に各論点を掘り下げて学習すると効果的です。
さらに、YouTubeやCPAラーニングなどの無料コンテンツもおすすめです。特にCPAラーニングでは、各論点の講義動画や模擬試験を無料で利用できるため大変便利です。筆者も、2級の試験学習の際はフル活用しました。
CBTのネット試験がおすすめ
簿記の本試験にはペーパー試験とネット試験の2種類がありますが、CBT形式で受けられるネット試験をおすすめします。
ネット試験はいつでも申し込み可能(本試験日の前後期間のみ受付停止)で、自分の学習進捗に合わせて試験日を選ぶことができます。また、試験終了後はその場で結果が分かるため、次に向けた行動がスムーズに進められます。さらに、前述したCPAラーニングにはネット模擬試験のコンテンツが用意されているため、気軽に試験対策ができます。
3級or2級?はたまた1級?初学者はどの級を目指すべきか
日商簿記には1級〜3級までのレベルが存在します。
どの級を目指すべきなのか、特に初学者の方は見当がつかないこともあるでしょう。
ここからは、各級でカバーできる範囲や難易度について紹介します。
一般企業への転職には2級で十分
一般企業の経理職では、簿記2級の知識で十分といえます。2級の試験範囲には、工場経理で必須な工業簿記や、親会社・子会社の連結会計など高度な知識も含まれます。経理職が未経験の方であっても、簿記2級の資格を持っていれば、経理職への適性やモチベーションを採用側にアピールできます。
資格を持っていれば実務で即通用するかと言うとそうではなく、簿記の知識が実務ではそのまま通用しない部分もありますが、簿記の原理を理解できていれば未経験者でも仕事の理解が早いでしょう。
まずは3級を受けるもよし、飛び級もよし
学生の方や基礎から固めたい方には、まずは3級の取得がおすすめです。3級で簿記の基本的な概念や仕訳の仕組みを学ぶと、その後の経理学習への土台となります。また、3級と2級は地続きのような関係で、出題範囲が重なる点も存在します。ネット試験で3級を受験し、合格すればその日のうちに2級の学習を始める、といった動き方も可能です。
一方で、簿記の事前知識が多少でもある方はいきなり2級に挑戦しても問題ないでしょう。
1級は難易度が高く、相応の努力が必要
簿記1級にはより複雑で専門的な内容が多く、公認会計士の受験資格を得るための基準ともなるほど高度な資格です。合格率は約10%程度と低く、学習時間も平均で1000時間以上が要求されるようです。
一般企業への転職を目的に取得する資格としては、オーバースペックともいえます。筆者も、簿記1級に挑戦する気は今のところありません。
ただし、公認会計士や税理士、大企業本社の経営管理本部で働くなど、レベルの高い場を目指すのであれば、挑戦しがいのある資格でしょう。
簿記の資格を活かせる業界と転職のコツ
簿記の資格を取得できたら、ぜひ転職に活かしたいものです。
まずは転職先として狙える業界や職種を紹介します。
そのうえで、履歴書や面接のシーンで好印象を残す必要があります。
アピールのコツもあわせて参考にしてください。
また、独立を目指す方や副業に取り組む方もいらっしゃるでしょう。
個人で仕事を請け負ったときは、確定申告の必要があります。
確定申告について知りたい方は、こちらの関連記事もご覧ください。
副業Webライター初めての確定申告!つまずきやすいポイントを解説
あらゆる業界の経理ポジション
簿記の資格を取得することで、業界を問わず経理職への道がひらけます。一般的な経理職では、日次の仕訳入力、月次・年次の決算に携わります。企業の財務状況を把握し、経営判断に関われる点がやりがいと言えるでしょう。
また、すでに経理職に就いている人も、簿記の資格を新たに取得するとスキルアップが図れます。より高度な知識を持って幅広い経理業務に対応できると、同じ職場での昇給や、転職先でのキャリアアップにつながります。
税理士事務所や会計事務所の補助ポジション
一般企業だけでなく税理士事務所も、簿記の資格を活かせる仕事の場です。税理士事務所の業務には、顧問先企業・個人事業主の仕訳入力を請け負う「記帳代行」が存在します。さまざまな業態の会計処理を経験できるため、簿記の知識を実務上で活かしやすい点が魅力です。
ちなみに、筆者の本業も税理士事務所での補助業務です。採用面接の際には、簿記2級が良いアピール材料になったと感じています。
履歴書や面接でアピールするコツ
まずは、転職のために資格を取ったことをアピールする姿勢が大切です。専門知識に加え、向上心も持っていることを示せるためです。また、経歴に空白期間がある方でも、資格勉強に要した時間であると説明すれば、ポジティブな印象を採用側に与えられるでしょう。
さらに、簿記の資格があっても経理職が未経験である場合は、現時点で実務スキルに乏しい部分を素直に認めたうえで、学習意欲や適性のアピールが重要です。あくまでも簿記の資格取得は目的ではなく、手段として利用できます。
まとめ
今回の記事では、簿記の資格が転職にもたらす影響について解説しました。
特に強調したいのは、経理や会計の人材はすべての会社にとって必要である点です。
そこで、簿記の資格は一定の経理知識とスキルを対外的に証明してくれます。
独学での合格も十分に可能であるため、経理への転職を目指す方にはぜひ挑戦していただきたいと思います。
ここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。
Photo by Recha Oktaviani(Unsplash)