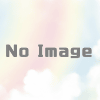第二新卒期間で円満に退職するには?手続きの流れやコツを経験者が解説
第二新卒は、新卒から3年目以内の人を指すケースが一般的です。
近年では転職の活性化や退職代行サービスの流行もあり、第二新卒期間での退職が多くみられます。
しかし中には、「石の上にも3年」や「せっかく就職できたのに」など周囲からの意見で退職をためらってしまう方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、第二新卒期間で退職した私が実体験をもとに、退職時の手続き方法やコミュニケーションのコツを解説させていただきます。
1. 退職の検討〜決断まで
なぜ退職したいのか、理由や原因を明確に
そもそも、退職を検討するようになった原因は何でしょうか。労働環境に不満がある、人間関係に悩んでいる、仕事のやりがいが見いだせない…など、まずは原因を洗い出してみましょう。
退職したい原因が分かれば、自分の労働に対する価値観も分かるはずです。
例えば、「自分は残業をしたくないんだ」「自分はチームプレーより個人プレーが好きだ」などです。
自分の価値観を知っておけば、退職後のキャリア構築にも役立ちます。
闇雲に不安を抱えたままにはせず、退職したい理由と原因を究明することから始めてみましょう。
退職以外の選択肢も洗い出し、比較検討する
最終的に退職を決断するとしても、他の選択肢と比較検討する価値はあります。
「退職」が一度頭によぎると、どうしても思考が短絡的になり退職一直線へと傾きがちだと思います。
勤務先の形態にもよりますが、勤務地の異動や職種の配置転換で環境を変えられるケースもあります。
会社に籍を置いたまま悩みを解決できる方法があるのであれば、退職してしまうよりそちらの方が楽かもしれません。
それぞれの選択肢のメリット・デメリットを洗い出して比較してみましょう。
周囲の意見を参考にしながら、決断は自分自身で
周囲の意見から、思わぬアイデアや考え方に行き着くこともあります。
親、友人、信頼できる同僚など、立場も年齢も異なる人に相談すると、多様な価値観が集まります。
また、そのアドバイスを受け容れるかどうかも自分次第です。
人生の決定権は自分自身にあることを忘れず、最後まで熟考したうえで決断するとよいでしょう。
2. 退職するまでの流れ
直属の上司・先輩に意思を伝えて手続き開始
退職までの流れは、意思伝達から始まります。
まず、直属の上司や先輩に話がある旨を伝え、会議室などで退職の意思を伝えます。引き止めに遭うかもしれませんが、自分で決めた事項は誠実に伝えることが重要です。
次に、日程や引き継ぎスケジュールを上司と相談し、具体的な計画を立てます。
そして、部署内で退職の報告を行い、引き継ぎ内容や今後の対応について共有します。
上記はあくまでも私が経験した流れですが、おおよそどこでも共通するかと思います。
担当業務の引き継ぎ、デスク周りの整理
ここからは、退職前の実務作業です。
引き継ぎ用のマニュアルを作成し、後任者に業務の流れやポイントを伝達します。また、仕事で使用していた資料は整理整頓して、デスク周辺をきれいに掃除します。
なお、当然ですが会社の備品は持ち帰らないようにしましょう。少額であっても窃盗罪にあたります。
これらの作業をすべて最終日に行おうとすると大変なので、前述したように引き継ぎスケジュールの策定は特に重要です。
“立つ鳥跡を濁さず"という言葉の通り、綺麗な形で会社を去れると理想ですね。
人事労務関係の書類手続き
退職後に必要な手続きを紹介します。
まずは社会保険の切り替えが必要です。新しい勤務先が決まっている場合はその会社で社保に加入し、それ以外の場合は国民健康保険に加入します。
あわせて、年金の切り替えも行います。お近くの役所で厚生年金→国民年金へと変更手続きができます。
すぐに再就職しない場合は、ハローワークで失業保険の手続きも行いましょう。あくまでも就労の意思があり、就職活動を継続していることが受給の要件です。
3. 第二新卒期間で退職するメリットとデメリット
【メリット①】目指すキャリアに向かって注力できる
素早い退職の決断によって、理想のキャリアに近づけるメリットがあります。
特に、理想とする退職後のキャリアが定まっていれば、若いうちからそこに向けて挑戦できるでしょう。前職で培ったばかりの経験を次の仕事で活かすことができる点も大きな利点です。
第二新卒期間であれば、研修等で学んだ基礎的なスキルが定着しているかもしれません。
【メリット②】時間に余裕が生まれ、スキルアップを目指せる
退職後の時間を利用して、資格やスキルの習得を目指すことができます。若い方は記憶の定着力も高く、新しい知識を素早く吸収してキャリアの幅を広げられるでしょう。
実際に私も、退職後に簿記の資格を取得して転職後に役立てました。自己啓発の面でも、実益的な面でも有効です。
【デメリット①】経験や技術が身につきづらい
新卒3年以内の経験しかない場合のスキルや技術は限られます。もちろん当人の努力次第ではありますが、経験年数の壁はどのみち存在するでしょう。また、全く異なる業界を志望するケースでは、前職の経験が活かしにくく、新しい環境への適応に時間がかかるかもしれません。
【デメリット②】金銭的な余裕を作りづらい
第二新卒期間では、基本給が高くないケースが多く、経験や技術の不足が収入に影響することがあります。成果主義の環境であれば高収入を得られる可能性もありますが、相応の能力が求められます。転職後は引っ越しなど環境の変化で出費がかさむこともあり、金銭面には苦しむかもしれません。
円満に退職するためのコツ
必要な情報のみを伝える
退職の意思や具体的なスケジュールを明確に伝えることが最も重要です。
また、退職の理由や根拠までを詳しく伝える必要はありません。思わず個人的な不満を漏らしてしまうと、無駄な対立を生むおそれがあります。
退職理由や今後の計画などプライベートな部分は、嫌でなければ軽く答える程度で構いません。
お世話になった方への挨拶を欠かさない
退職前に、同僚だけでなく他部署や取引先の方々にも挨拶すると好印象を持たれるでしょう。会社から身を引いたとしても、将来別の仕事や取引で関係者と再会する可能性がないとは言い切れません。その際に悪い印象が残っていると、仕事に直接悪影響が出ます。
良好な関係を保ちつつ、新たなステップに進むことができると理想的です。
退職後の動き方を事前に決めておく
退職後の行動計画は可能な限り事前に決めておきましょう。
やりたい仕事がないと、無収入が続くだけでなく心理的な不安も生じやすくなります。すぐに再就職するか、失業保険を利用するかなど、具体的な動きを決めておくと安心です。
もちろん、退職前に内定をもらっておき、即転職することも素晴らしい選択です。
まとめ
今回は、退職手続きの流れや成功させるコツを解説しました。
円満に、スムーズに退職するには、入念な事前準備に尽きると考えます。
第二新卒での退職は、少なからず罪悪感や不安を感じてしまうものかもしれません。
しかし、お世話になった人たちへの感謝を忘れず、自分の明確な意思を伝えられると、関係者からは今後の人生を応援してもらえるのではないでしょうか。
この記事が転職を検討している方の参考になることを願っております。
ご覧いただきましてありがとうございました。