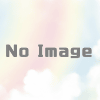全フリーランスが労災保険に加入できる今、Webライターが補償を受けられるケースは?
労災保険は、業務中や通勤中の事故によって発生した怪我、病気を補償する公的制度です。2024年11月から、フリーランスが労災保険の加入対象に加わりました。これによって、業務委託で仕事を受注するWebライターも労災保険の恩恵を受けられます。この記事では、Webライターが受けられる補償の具体的なケースを考察します。
労災ってサラリーマンのものじゃないの?
今はフリーランスも加入できますぜ
現在、ほとんどのフリーランスは労災保険への加入が可能
元来の労災保険は、労働者(会社員)が業務中や通勤中に被った事故を補償する制度でした。
近年では、フリーランスや個人事業主など雇用関係のない方も労災保険に加入できます。
労働局から承認を受けた特定の加入団体を通じて、労災保険への「特別加入」が可能です。(※1)
危険を伴う業務以外でも、日常業務で起こりうるケガや病気に備えられる点がメリットです。
万が一のリスク対策として、有効な選択肢のひとつになるでしょう。
フリーランスが労災保険に加入して受けられる補償内容
労災保険を活用すると、業務中のケガや病気に対して医療費や休業補償の給付を受けられます。
会社員とフリーランスに補償内容の差はなく、障害が残った場合の年金給付や、遺族給付なども補償範囲に含まれます。(※2)
Webライターの場合は、取材中の事故や執筆中に生じた疾病が対象になる可能性があります。
加入者が増えると、フリーランスで“労災がおりる”ケースは今後増加すると予想できます。
フリーランスが労災保険に「特別加入」する手続きの流れ
特別加入は、特定フリーランス事業の特別加入団体に申し込むことで手続きが可能です。
2025年6月時点では、7団体が厚生労働省のWebサイトで紹介されています(※3)。
申請には加入要件の確認や保険料の納付が必要です。
特別加入団体の公式サイトを確認してみましょう。
(例:連合フリーランス労災保険センター)
煩雑な事務手続きは加入団体に一任でき、サポート体制も充実しています。
労災保険で補償を受けられるケガ・病気の範囲
補償対象は、業務中か通勤中の事故が原因で発生したケガや病気に限定されます。
仕事と事故の因果関係が争点ですが、個人での判断は難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで役に立つ資料が、労働基準法施行規則に示された「職業病リスト」です。(※4)
事故に伴うケガ、病気が職業病リストに記載されていれば、労災の補償を受けられます。
個人事業主は万が一に備える労災保険が重要
フリーランスは会社員と比較すると収入を安定させづらい側面があり、ケガや病気で働けなくなると生活の維持が難しくなるリスクも存在します。
そこで労災保険に入っていれば、万が一の場合に療養費や休業補償が支給され、生活リスクに備えられます。
Webライターは業務上のケガや病気のリスクが小さい部類の職種ではありますが、誰の身にもいつ何が起こるかは分かりません。
フリーランスの労災保険は、非常時に生活を維持するための意義が大きい制度です。
補償は受けられる?Webライターが直面するトラブルの具体例を検討
続いて、Webライターの業務中に発生するおそれのあるケガ、病気について労災の観点で検討してみましょう。
「職業病リスト」に記載される事柄であれば労災の補償を受けられます。
屋外での取材活動、在宅での執筆を問わず、予想だにしないリスクが存在します。
例①:取材での移動中、事故に遭遇
取材中の移動中に遭遇した事故は、「業務中」と判断されやすい事例のひとつです。
自宅から取材先への移動であれば「通勤中」とみなせます。また、アポイント間の移動で生じた事故は、ライターにおける業務災害の典型例といえます。
たとえば取材場所に向かう途中で転倒してケガを負った、または交通事故に遭って入院した場合、労災として認定されて給付を受けられる可能性が高いでしょう。
例②:タイピングによる腱鞘炎
Webライターは執筆業務に際して、PCでのタイピング作業がつきものです。
日常的な執筆作業の積み重ねで腱鞘炎を起こしたときは、労災と認められる可能性があります。
反復作業による「職業性疾病」に該当するかどうかが、労災の判断基準です。
職業病リストには、「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」(引用:厚生労働省|職業病リスト三・4)という記載があります。
タイピングができなければ執筆は困難で、その期間は収入が落ち込むリスクがあるため、労災保険での備えが大切です。
例③:長時間の執筆による肩や腰のトラブル
執筆による肩こりや腰痛も、業務内容と因果関係が認められれば労災対象となり医療費の給付を受けられます。
とくに長時間にわたる同一姿勢が原因で慢性疾患が悪化した場合などが該当します。
腱鞘炎のケースと同様に、職業病リストより「後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」を根拠規定として利用できるでしょう。
案件が集中すると、Webライターは長時間にわたってデスクワークを強いられる場合があります。自己管理の範囲、と考えてしまう方もいるかもしれませんが、程度によっては労災の補償が受けられます。
これらは労災保険の対象外!Webライターに起こりうるその他のトラブル
クライアントの公開前情報漏らして損害出しちゃったけど、
労災おりるんじゃないの???
いやいや、、、
クライアントから受領した機密情報の漏えい
クライアントの機密情報を流出させて、万が一損害賠償請求の訴訟を起こされてしまっても、労災の補償対象にはなりません。
労災保険は“身体的被害”が前提であり、情報管理やセキュリティ上のミスは対象外です。
このようなリスクに対しては、別途「賠償責任保険」の対策が有効です。前提として、漏えいリスクのある環境(フリーWi-Fi、人の多いカフェ)では仕事をしない意識も求められます。
情報漏えいトラブルには、自ら備える必要があります。
虚偽の内容やコピペによる訴訟リスク
納品物の内容が原因で訴訟にまで発展した場合も、労災保険の範囲外となります。
たとえ仕事中に発生した事故であっても、労働者が被った損害ではないためです。
とくに、虚偽内容の執筆や他サイトからのコピペは厳しく責任を追求されるおそれがあります。
法的リスクを避けるには、正確なリサーチとコピペチェックの徹底が重要です。
Webライターは手軽に始められる一方で、法的トラブルに発展するおそれもある点は認識しておきましょう。
PCが壊れて執筆できない
パソコンの不具合やクラッシュで仕事ができなくなっても、休業補償は受けられません。
経済的な損失ではありますが、身体に被害が及んでいないため労災の定義外となります。
バックアップ体制や予備のデバイスを用意しておくと、万が一のトラブル時に役立ちます。
フリーランスは突発的な機器トラブルに弱い一面がありますので、代替機や緊急時のマニュアルを自分で用意しておくと安心できるでしょう。
「仕事のトラブルすべて=労災」ではない
「仕事中のトラブルだから、全部労災でカバーできるでしょ?」→これは誤解です。
労災保険の対象は、「業務中または通勤中」で「業務が原因」のケースに限られます。
PCの故障や情報漏えい、執筆内容の不備によるトラブルなどは対象外です。
経済損失や訴訟リスクについては別途、日頃の備えや民間保険で自衛する必要があります。
労災保険の恩恵を受けたいのであれば、補償の線引きを知っておくことが重要です。
参考文献
- (※1)厚生労働省|令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました
- (※2)厚生労働省|どんな補償が受けられるか?
- (※3)厚生労働省|特定フリーランス事業の特別加入団体(加入手続)
- (※4)厚生労働省|職業病リスト
Photo by Nick Morrison(Unsplash)